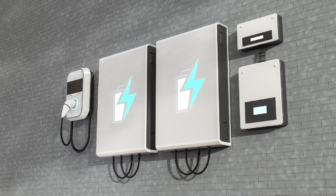今年、太陽光発電の普及が進んでいるなかで、売電単価の低下が続いています。
売電単価は、約16円まで下がると予測されており、売電収入だけに依存するのは厳しい時代がやって来ました。
この記事では、現在の売電限界の状況や今後の経過、さらに売電限界の低下にどう対応すべきかを詳しく解説します。
また、太陽光パネルの設置費用の回収シミュレーションや、補助金制度の活用方法についても紹介し、経済的にメリットを得るための具体的な方法を提案していきます!
売電単価の現状
2025年以降の売電期間は、過去と比べて大きく下がる可能性が高いと予測されています。
現在の売電単価がどれぐらいなのか、またなぜ下がり続けているのかを詳しく見ていきましょう。
2025年の売電単価はどれくらい?
2025年度の売電単価は、2023年・2024年度と同様に16円/kWh(10kW未満)
で据え置かれる可能性があります。
発電容量 2023年度 2024年度 2025年度(予測) 10kW未満 16円/kWh 16円/kWh 16円/kWh 10kW以上50kW未満 10円/kWh 9.2円/kWh 8.5円/kWh 50kW以上 9.5円/kWh 9.2円/kWh 8.0円/kWh
このように、規模が大きい発電ほど売電単価は低下傾向にあり、2030年ごろにはさらに下がると予測されています。
売電単価が下がる理由とは?
売電単価の低下には、以下のような主な理由があります。
①太陽光発電の普及による市場原理
太陽光発電の導入が進み、電力の供給量が増えることで、市場価格が下がり続けています。
特に、大規模なメガ太陽光施設の増加により、発電コストが安くなり、売電価格も低下する傾向にあります。
②再エネ賦課金の抑制
売電税率は「FIT制度(固定価格買取制度)」によって決められますが、この制度の財源は「再エネ賦課」として国民の電気料金に上乗せされる形で賄われています。
再エネ賦課金の負担増加を重視するために、政府は売電価格を低く設定しているのです。
売電単価の今後の推移
現在、売電期限は年々低下しており、この傾向は今後も続くと考えられています。
特に、2030年までの売電期限の経過については、多くの専門機関がシミュレーションをおこなっています。
ここでは、今後の売電早期の予測と、その低下にどう対応すべきかを解説します。
2030年度までの売電単価予測
経済産業省は、太陽光発電の売電価格を段階的に検討する方針を示しています。
特に、住宅用の10kW未満の売電限界は、以下のように推移する可能性が高いとされています。
年度 売電単価(10kW未満) 2023年 16円/kWh 2024年 16円/kWh 2025年 16円/kWh(予測) 2026年 14円/kWh(予測) 2027年 12円/kWh(予測) 2028年 10円/kWh(予測) 2029年 9円/kWh(予測) 2030年 8.5円/kWh(予測)
このように、2030年には8.5円/kWhまで下がると予測されています。
50kW以上の産業用太陽光では、すでに9円/kWhを下回っているため、住宅用の売電単価も今後さらに下落する可能性が高いでしょう。
また、FIT制度終了後は売電上限が市場価格(FIP認定など)に受け入れられるため、より不安定になると考えられます。
売電単価低下への対応
売電が低下するなか、太陽光発電を導入するメリットを最大化するためには、以下のような対策が重要です。
①自家消費をメインにする
売電料金が低くなったとしても、電力会社から電気を購入するコスト(電気代)は上昇傾向にあります。
そのため、売電収入を増やすよりも、発電した電力を自家消費して電気代を節約することが可能です。
特に、日中の電気使用量が多い家庭では、太陽光パネルと蓄電池を活用することで、さらに節約効果が高められます。
②売電単価の高い電力会社を選ぶ
FIT制度終了後は、卒FIT(固定価格買取制度が終了した後の売電)に対応する電力会社を選ぶことが重要になります。
電力会社によって買取価格が異なるため、事前に調査し、最も高く買ってくれる会社を選ぶことで、売電収入を最大化できます。
③高効率の太陽光パネルを導入する
発電効率の高い太陽光パネルを選ぶことで、同じ地域の屋根でもより多くの電力を感じます。
長期的な視点で見れば、高性能なパネルを導入することで、売電収入と電気代の削減効果を高めることができます。
売電単価を最大限に活用するための3つのポイント
売電料金が年々低下するなかでも、太陽光発電を賢く活用することで、電気代の節約や売電収入の最大化が可能です。
ここでは、太陽光発電の導入メリットを最大限に引き出すための3つのポイントを紹介します。
ポイント①自家消費をメインにする
売電が低下している現状において、太陽光発電を効果的に活用するためには、自家消費を優先することがポイントとなります。
従来のように、売電による収入を重視するのではなく、発電した電力を自宅で直接使用することで、電気代を大幅に削減することが可能です。
特に、日中の電力使用量が多い家庭や、在宅勤務が増えている場合には、自家消費のメリットはとても大きいと言えます。
自家消費を効果的におこなうためには、生活スタイルを見直し、太陽光発電で降りた電力を積極的に使うと良いでしょう。
電飾消費が多い家電を昼間の発電時間帯に稼働させることで、余剰電力を減らし、電力会社から購入する電気量を削減させることができます。
また、蓄電池を併用することで、日中に発電した電力を夜間にも利用することが可能となり、さらなる電気代の節約にも期待できます。
さらに、エコキュートや電気自動車の充電など、自家消費を促進するための設備を導入することで、発電した電力を最大限に活用することが可能です。
このように、自家消費をメインとすることで、売電単価の低下に対しても、安心した経済効果を得ることができます。
ポイント②発電効率の高い太陽光パネルを選ぶ
売電の低下が続くなかで、太陽光発電システムの導入効果を最大化するためには、発電効率の高い太陽光パネルを選択することが重要です。
同じ居住の屋根でもより多くの電力を作ることが可能となり、結果として売電収入や電気代削減効果を向上させることができます。
高効率な太陽光パネルは、変換効率が20%以上のものが一般的であり、最新の技術を主張したパネルでは22%を超えるものもあります。
このようなパネルを導入することで、日射量が少ない曇りの日や冬場でも安定した発電が期待できるため、年間子育て高い発電量を確保できます。
また、製品保証や出力保証が無意識に提供されているパネルを選ぶことも重要です。
例えば、25年間の出力保証があるパネルでは、設置後も一時的に安定した発電が見込めます。
初期投資を早期に回収し、その後の売電収入や電気代削減による利益を最大さらに、高効率なパネルは設置スペースが限られている場合でも十分な発電が可能であり、小さな屋根にも適しています。
高効率のパネルを選ぶことは、長期的な経済効果を確保するための賢明な選択と言えます。
ポイント③卒FIT後に最適な電力会社を選ぶ
FIT制度(固定価格買取制度)は、10年間の購入期間が設定されています。
そのため、FIT期間が終了すると、電力会社との直接契約が必要になります。
このとき、どの電力会社と契約するかで売電収入が変わるため、慎重に選ぶことが重要です。
各電力会社の卒FIT後の売電価格は、以下のとおりです。
電力会社 売電価格(卒FIT後) 国際 8.50円/kWh 関西電力 8.00円/kWh 中部電力 7.00~12.00円/kWh 東北電力 9.00円/kWh 九州電力 7.00円/kWh 北海道電力 8.00円/kWh
卒FIT後の売電価格は、FIT制度中の売電上限よりも低くなるため、蓄電池を活用して自家消費を増やすことが賢い選択になります。
太陽光パネル設置費用の回収について
太陽光発電システムを導入するとき、多くの人が気になるのが「初期投資の回収期間」です。
売電費の低下が続いているものの、発電設備の価格も年々下がっており、適切に活用すれば設置費用の回収は十分に可能です。
ここでは、具体的な回収シミュレーションや補助金制度の活用方法について解説します。
設置費用の回収シミュレーション
一般的な住宅用太陽光発電システム(5kW程度)の導入費用は、補助金なしの場合約130万円が相場です。
では、どのくらいの期間で設置費用を回収できるのか、以下のシミュレーションを見てみましょうしょう。
項目 設置前 設置後(売電+節電) 月間電気代 15,000円 8,000円 月間売電収入 なし 5,000円 年間維持費 なし 15,000円 年間収支(売電+節電効果) -180,000円(支出) -51,000円(支出) 費用回収年数(補助金なし) – 約11年 費用回収年数(補助金あり) – 約6年
売電収入と電気代の節約効果を合わせて考えると、補助金なしでも約11年、補助金を活用すれば約6年で初期投資を回収できる計算になります。
また、太陽光パネルの寿命は20〜30年とされているため、費用回収後も約20年間は売電収入と節電効果による利益を得ることができます。
補助金制度を活用してお得に設置
太陽光発電システムの設置費用を考えるためには、国や自治体の補助金制度を活用することが重要です。
補助金を利用することで、初期費用を削減し、回収期間を短縮することが可能です。
主な補助金制度は、以下のとおりです。
- 国の補助金(環境省・経済産業省)
- 例:住宅用太陽光発電導入支援事業
- 1kWあたり2〜5万円程度の補助
- 地方自治体の補助金
- 自治体ごとに異なるが、1kWあたり3〜10万円の補助がある地域も
- 例:東京都「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」
- 蓄電池併用の補助金
- 太陽光パネル途中蓄電池を導入することで、追加の補助金が受けられる場合がある
補助金の対象や金額は自治体によって異なるため、設置を検討するときには必ず最新の情報を確認し、利用できる制度を最大限活用しましょう。
太陽光パネルと蓄電池の併用効果
売電単価が低下するなか「で、より高い経済利益を得るために蓄電池の併用がとてもに効果的です。
蓄電池を導入することで、太陽光発電の電力を夜間にも活用でき、電気代の削減効果をさらに高めることができます。
【蓄電池のメリット】
- 発電した電気を夜間にも使える
- 緊急時のバックアップ電源として利用できる
- 卒FIT後も電力を最大限に自家消費できる
例えば、5kWの太陽光発電と6kWhの蓄電池を併用した場合、以下のようなシミュレーションになります。
設置条件 費用回収年数(補助金なし) 費用回収年数(補助金あり) 太陽光発電のみ 11年 6年 太陽光発電+蓄電池 17年 10年
蓄電池の導入には追加のコストがかかるものの、補助金を活用すれば約10年間で回収可能です。
また、電気代の確保に備えて電力の自家消費を増やすことができるため、長期的には経済的なメリットが大きくなります。
売電単価に関するまとめ
近年、太陽光発電の普及が進んでいますが、売電単価は低下を続けています。
そのため、売電収入に頼るのではなく、自家消費をメインとした活用が求められています。
発電した電気を効率的に使うためには、日中に電力を使う工夫や、蓄電池を併用して夜間の電力を自家消費することが効果的です。
蓄電池を選ぶことで、限られた屋根スペースでもより多くの電力を得ることができます。
設置費用については、補助金を活用すれば6年程度で回収可能となり、その後は当面経済的なメリットを得ることができます。
補助金制度の活用や電力契約の見直しを含め、賢く太陽光発電を活用していきましょう。