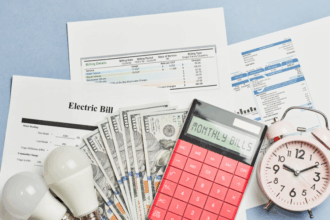太陽光発電を検討する人が増える中で、蓄電池の導入もよく話題になります。
停電に備えたい、あるいは電気料金を抑えたいという理由で気になる方も多いでしょう。
自身の住宅環境や暮らし方によっては、導入しないほうが良い場合もあるのです。
この記事では、蓄電池を設置しないほうがいいケースや理由、そして見送ったほうがいい具体的な家庭の特徴などを紹介します。
あわせて、導入を検討する前に確認しておきたいポイントもまとめました。
蓄電池をやめたほうがいい3つのケース
ここでは、蓄電池導入であまりメリットを得られなさそうなケースを取り上げます。
生活スタイルや住環境によっては、元々の電気料金が低額だったり、停電リスクが少なかったりします。
また、設置自体が物理的に難しい住宅もあるかもしれません。
以下の3つのケースに当てはまるなら、いったん導入を見送る判断も考えてみてください。
電気料金が既に低額な世帯
電気使用量が少ない家庭では、月々の電気代がすでに低めであることが多いです。
蓄電池は放電や充電を行うことで電気代をコントロールできるのが魅力ですが、元々の出費が小さい場合、その恩恵は大きくありません。
また、電気代が安いと蓄電池の初期投資を回収するまでの期間が長くなりがちです。
特に、夜間に電力をあまり使わず、昼間の太陽光発電だけで大半の電力をまかなえているなら、導入による差はさらに小さくなります。
停電リスクが低い地域
蓄電池の導入を考える大きな要因の一つが停電対策です。
地震や台風が多い地域では、非常電源があると安心感があります。
しかし、比較的災害が少なく、近年ほとんど停電を経験しないエリアに暮らしているなら、蓄電池を常に備えておく必要性はそこまで高くないかもしれません。
ただし、いつ起こるかわからない災害に備える意味はあるので、今の暮らしにどれだけリスクを感じるかをよく考えてみる必要はあるでしょう。
設置スペースに制約がある住宅
蓄電池は屋外や屋内にある程度のスペースが必要です。
戸建て住宅でも、敷地が狭いと外に大きな機器を置くのが難しいケースがあります。
また、蓄電池を置ける場所があっても、周囲に障害物が多いと施工の自由度が下がり、追加費用もかさんでしまいがちです。
もし大幅なリフォームをしないといけないほどの制約があるなら、費用対効果を冷静に考えてみる必要があります。
蓄電池設置を見送るべき5つの理由
次に、蓄電池をわざわざ設置しなくてもいい、あるいは導入するハードルが高い主な理由を整理します。
補助金の条件や、機器の保証の話なども含まれます。
これから蓄電池を検討する人は、実際にこれらの点が自分の状況と合うかどうかをチェックしてみてください。
メンテナンス費用の負担
蓄電池は一度設置したら終わりではなく、定期的な点検や部品交換が必要になる可能性があります。
機器の状態を保つためにも、ある程度のメンテナンスが欠かせません。
その費用を長期間にわたって負担できるかどうかを考えておく必要があります。
メンテナンス契約がセットになっていることもありますが、そのぶん月々の支払いが増えることもあります。
補助金対象外となるパターン
自治体によっては蓄電池の補助金制度が用意されていますが、すべての人が申請できるわけではありません。
申請条件を満たさないと、結果的に自力で全額を負担することになります。
また、締め切りや予算の都合で、希望していても間に合わない場合もあります。
補助金を当てにして導入を考えていた人にとっては、目安が狂ってしまう大きなリスクといえるでしょう。
太陽光発電効率への影響
蓄電池と太陽光発電を組み合わせると、発電した電力を無駄なく使えるメリットがあります。
ですが、どのように配線するか、パワコンの性能や設置場所などによっては、太陽光の発電効率が下がる可能性があります。
極端に効率が落ちるわけではないにしても、最適な組み合わせをしないと、思ったほど電気代が下がらないこともあるのです。
パワコンの保証期間との関係
蓄電池と太陽光発電を連携させるには、パワコン(パワーコンディショナー)という装置が重要になります。
パワコンの寿命や保証期間によっては、蓄電池を新しく導入しても、パワコン自体を近い将来交換しなければならないかもしれません。
そのタイミングが合わずに、結局余分な費用が発生してしまうケースもあります。
蓄電池だけでなく、パワコンの状態も含めて検討しておかないと、後から思わぬ出費につながります。
初期投資の回収期間
蓄電池は決して安い買い物ではありません。
初期投資分を電気代の削減や売電収入で回収できるまでには、どうしても数年から十数年単位の期間が必要になります。
その間、ライフスタイルの変化や電気料金のプラン変更など、状況が大きく変わる可能性もあります。
投資を回収する前に住宅を手放すことになったり、家族の人数が減って電気使用量が下がったりすると、期待していたほどのメリットを得られないかもしれません。
蓄電池が不要な3つの家庭環境
次に、暮らし方や住宅設備の側面から、蓄電池があまり必要ないと思われる環境を見ていきます。
日常的な電力消費のパターンや、すでに整っているシステムなどによっては、蓄電池を追加しても大きな効果が見込めないことがあります。
ここでは3つの例を挙げ、具体的にどういう状況なら導入を考えなくてもよいかを述べます。
日中の電力消費が中心の生活
家族全員が昼間に家にいない場合、日中に太陽光で発電しても、それを活用しきれず売電に回すことが多いでしょう。
逆に、在宅時間が長く日中も電気を使う家庭は、蓄電池よりも太陽光の直接利用で電気代を抑えられる場合もあります。
夜間はあまり電力を使わないなら、蓄電池でわざわざ昼の電気をためておく必要性はそこまで高くないかもしれません。
ただし、深夜に電気をよく使う家庭なら、蓄電池のメリットは大きくなることもあるため、自分たちの生活リズムと照らし合わせるのが大切です。
オール電化設備が整っている住宅
オール電化の家庭では、深夜電力の料金が安いプランを利用していることが多いです。
このプランだと、夜間に電気をまとめて使ってもさほど高い料金になりません。
そのため、蓄電池にためておいた電気を使わなくても、日中の太陽光発電分を売電して、夜間は安い電気を買うという形でコストを下げることができるケースがあります。
蓄電池を導入しても、割安な深夜電力の魅力がある以上、投資コストの回収はやや長くなるでしょう。
売電価格が高い契約世帯
昔に契約をして、今でも比較的高めの売電価格が設定されている世帯もあります。
高単価で買い取ってもらえるうちは、余剰電力をなるべくたくさん売ったほうが収益につながりやすいです。
蓄電池を導入すると、自家消費を増やして電気代を下げるメリットはありますが、そのぶん売電分が減る可能性もあります。
結果として、売電価格が高い時期は蓄電池の恩恵が少なくなることもあるのです。
蓄電池導入前に確認すべき3つのポイント
ここまでの話を踏まえたうえで、やはり導入すべきか迷っているなら、最終的に押さえておきたい確認事項があります。
特に電気の使用量や料金プラン、それから太陽光発電の性能や災害リスクを含めた安心感などは大きな要素です。
以下の3つの視点をきちんと整理したうえで、導入の是非を判断しましょう。
電気使用量と料金プラン
まずは、実際にどれぐらいの電気を使っているか、過去の検針票などでしっかり確認してみましょう。
そのうえで、自宅がどんな料金プランに加入しているかも要チェックです。
オール電化プランなのか、一般的な従量電灯なのかなどによって、蓄電池から得られるメリットは変わります。
実際に数字として試算してみると、「思ったより効果が小さい」「投資額が大きい」といったことが見えてくるはずです。
太陽光発電の発電効率
蓄電池は太陽光発電と組み合わせてこそ本領を発揮する部分があります。
ですが、太陽光のパネルが古くなっていたり、設置場所の影響で発電量が十分でなかったりすると、期待値ほど効果が出にくいかもしれません。
経年劣化や屋根の角度、季節による日射量など、細かい要素も大事です。
もし太陽光の発電量が少ないなら、その原因を明確にしたうえで対策を考えたほうがいいでしょう。
災害リスクの評価
停電がまったく起こらない保証はありません。
台風や地震が心配な地域に住んでいるなら、蓄電池を導入しておくと非常時に役立ちます。
電気が途絶えても、蓄電池に貯めた電力があれば、最低限の生活を維持しやすいからです。
ただし、停電リスクがそれほど高くない地域だと、コスト負担に見合うほどのメリットが得られないかもしれません。
自分の地域の災害情報や避難所の状況なども含めて、よく検討することをおすすめします。
まとめ
蓄電池が注目される背景には、電気代の高騰や災害への備えなど、さまざまな要因があります。
しかし、実際には初期費用やメンテナンス、発電効率とのバランスなどを考慮すると、導入をためらう人も多いのが現実です。
自分の電気使用量や住んでいる地域の停電リスク、補助金や保証の条件などを冷静に見極めることが大切といえます。
本当に必要だと判断できる環境なら導入を検討すべきですし、デメリットが大きいようなら見送るのも賢い選択です。
まずはこの機会に、家計や生活スタイルに合った方法を検討してみてください。