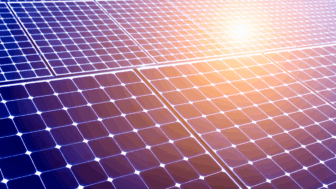近年、世界的な資源価格の変動や国際情勢の影響により、電気代や燃料費が上昇傾向にあります。
特に日本では、エネルギーの多くを輸入に依存していることから、円安や国際市場の不安定さがエネルギーコストの上昇に直結しています。
製造業では、生産に必要な電力や熱のコストが増加し、経営に与える影響が大きくなっています。
また、企業に対しては環境への取り組みも一層重視されるようになっています。
SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルの実現に向け、エネルギーの効率化や温室効果ガスの削減が求められています。
省エネへの取り組みは、コストの見直しだけでなく、社会的な信頼や企業価値の向上にもつながります。
ここでは、大きな設備投資を伴わずに始められる、工場向けの省エネ対策を8つご紹介します。
省エネの第一歩として、ぜひご活用ください。
工場の省エネアイデア8選
エネルギーコストの上昇が続くなか、工場でできる省エネ対策への関心が高まっています。
無理なく始められ、実際に効果が出やすい取り組みを中心に、ここでは8つの実践的な対策を紹介します。
日々の運用に取り入れることで、コストの見直しと環境負荷の軽減につなげていきましょう。
アイデア①照明の見直し|LED化と人感センサーで即効節電
工場内の照明をLEDに切り替えることで、消費電力を大幅に削減できます。
さらに、人の動きに反応する人感センサーやエリアごとのゾーン照明を導入することで、使わない時間帯・場所の無駄な点灯を防ぎ、効果的な節電が期待できます。
アイデア②空調管理
空調は電力消費が多い設備のひとつです。
適正な温度設定や外気との自動連動、使用時間の制限などで、快適性を維持しながら省エネを図ることが可能です。
空調機器のフィルター清掃や定期点検も、効率の維持に欠かせません。
アイデア③生産設備の効率化|老朽機器の入れ替えと定期メンテ
老朽化した生産設備は、稼働効率の低下だけでなく、余分なエネルギー消費の原因にもなります。
可能な範囲で新しい高効率機器への更新を検討し、日常の点検や予防保守を行うことで、安定稼働と省エネの両立が図れます。
アイデア④断熱・遮熱施工
屋根や外壁の断熱・遮熱性能を高めることも、省エネ効果の高い対策です。
夏場の冷房負荷、冬場の暖房負荷を抑えることで、空調にかかるエネルギーの削減が可能です。
建物全体の熱環境を見直すことは、空調管理とも連動した効果が期待できます。
アイデア⑤再生可能エネルギーの導入
太陽光発電などの再生可能エネルギーを導入すれば、自家消費による電気代削減が可能になります。
蓄電池やV2H設備を組み合わせることで、ピークカットやBCP(事業継続計画)対策としても有効です。
補助金制度も充実しており、導入コストの抑制も見込めます。
アイデア⑥電力会社・電気料金プランの見直し
現在契約している電力会社や料金プランが、自社の使用パターンに合っているかを確認することも省エネの一環です。
需要のピーク時間や基本料金の算出方法を見直すことで、実際の使用量が変わらなくても電気代を抑えられる可能性があります。
アイデア⑦運用ルールの徹底
省エネの基本は、不要な機器の「電源を切る」ことです。
照明や空調、コンプレッサーなど、稼働していない時間帯にはしっかりと停止する運用ルールを徹底しましょう。
職場全体で「使わないときは止める」を意識するだけでも、着実な削減につながります。
アイデア⑧点検・管理の習慣化
日常の点検やデータの記録を通じて、エネルギーの使用状況を把握することが省エネの第一歩です。
小さな異常や無駄に気づくことが、大きな改善につながることもあります。
エネルギー使用の「見える化」を進めることで、社内全体の意識も高まりやすくなります。
これらの取り組みは、どれも特別な設備投資をしなくても始めやすいものです。
コスト削減だけでなく、環境配慮への取り組みとしても意味があり、社内外への良いアピールにもつながります。
まずはできることから、少しずつ実践していくことが大切です。
工場の省エネアイデアは補助金活用で賢く導入
省エネ対策の必要性が高まる中、導入コストを抑える方法として「補助金制度の活用」が注目されています。
特に、工場や事業所向けの設備更新・省エネルギー対策には、国や自治体によるさまざまな支援策が用意されています。
ここでは、制度の概要と活用のポイントについて3つの視点からご紹介します。
①資源エネルギー庁が紹介する主な制度
資源エネルギー庁では、工場や事業所が省エネ対策を進めるために利用できる補助金・税制優遇・融資制度について、公式サイトでわかりやすく紹介しています(制度一覧はこちら)。
たとえば、「省エネルギー投資促進支援事業(補助金)」では、空調や照明、熱源機器などの高効率設備の導入に対して経費の一部が補助されます。
また、「中小企業等経営強化法に基づく税制措置」では、一定の省エネ設備を導入した際に即時償却や特別償却が認められる場合があります。
どの制度が利用可能かは、事業の内容や導入設備によって異なるため、早めに情報を把握し、活用の可能性を検討することが大切です。
②補助金と税制優遇・融資支援の違いと特徴
省エネ支援制度には、「補助金」「税制優遇」「融資支援」という3つの主な形があります。
それぞれの特徴を把握して使い分けることが、導入計画の成功につながります。
補助金は、導入にかかる費用の一部が国や自治体から支給される制度で、資金的な負担を直接軽減できます。
ただし、申請時期が限られており、要件を満たす事業計画や報告が必要になります。
税制優遇は、設備投資に対して減税措置が適用される制度で、資金の出入りに影響せず、法人税の負担を抑えられる点が特長です。
補助金と比べて手続きが比較的簡単で、長期的にメリットが得られる場合もあります。
融資支援は、省エネや脱炭素に取り組む企業に対し、低利・長期の融資を提供するもので、まとまった資金が必要な大型設備更新などに適しています。
これらの制度は、併用できる場合もあるため、自社の計画や資金繰りに応じて適切な組み合わせを選ぶことが重要です。
③国・自治体・支援機関の役割と使い分け
省エネ支援制度は、国、地方自治体、支援機関(商工会議所や地域の産業振興センターなど)がそれぞれ異なる役割を担いながら展開しています。
国は、主に大規模な支援制度や中長期的な方針に基づいた補助事業を展開しており、全国を対象とした制度が中心です。
省エネルギー投資促進事業やSHIFT事業などが代表例です。
自治体は、地域特性に応じた独自の補助金制度を設けている場合が多く、中小企業の設備更新や再エネ導入を対象に、比較的柔軟な制度設計がなされていることが特徴です。
補助率が高めに設定されていたり、申請サポートが手厚かったりするケースもあります。
また、支援機関は申請にあたっての相談窓口としての役割を担っており、制度の選定や申請書類の書き方、計画づくりの支援などを行っています。
とくに初めて補助金を活用する場合には、地域の支援機関への相談が有効です。
それぞれの役割を理解し、自社のニーズに合った支援先を選ぶことで、より実効性の高い省エネ投資が可能になります。
補助金制度は年ごとに内容が見直されるため、最新情報を把握し、導入スケジュールと合わせて計画的に進めることが大切です。
制度の選定から申請、実行までをしっかりサポートしてくれる専門業者や支援機関と連携し、無理のない省エネ導入を目指しましょう。
工場の省エネは電力契約+太陽光導入から始めよう
工場における省エネの取り組みは、日常の運用の見直しから設備投資まで幅広くありますが、まず手をつけやすく、かつ効果が見込めるのが「電力契約の最適化」と「太陽光発電の導入」です。
ここでは、短期的・長期的に分けて2つの観点からご紹介します。
①今すぐできる省エネアイデア=電力会社の見直し
工場や事業所で契約している電力プランは、実際の使用状況に合っているでしょうか。
使用電力量そのものを減らさなくても、「契約先の電力会社」や「料金プランの見直し」によって電気料金を削減できるケースは少なくありません。
特に、高圧契約を結んでいる工場では、「基本料金の算定方法」や「ピーク時間帯の単価」などが大きく影響します。
これらを正しく把握し、自社の使用パターンに合った契約形態へ見直すだけでも、毎月の電気代を抑えることが可能です。
また、再エネ比率の高い電力プランを選ぶことで、環境への配慮を示す取り組みとして社外へのアピールにもつながります。
見直しには負担が少なく、比較的短期間で結果が出やすいため、省エネ対策の第一歩として有効です。
②長期的に取り組む省エネアイデア=太陽光発電の導入
一方で、中長期的に省エネを進めるなら、太陽光発電の導入が有効です。
屋根や敷地を活用した自家消費型の太陽光発電は、日中の電力使用を再生可能エネルギーで補うことができ、電力購入量そのものを減らすことが可能です。
初期費用がかかるイメージがありますが、近年は国や自治体の補助金制度が充実しており、自己所有だけでなくPPA(第三者所有)やリースによる初期費用ゼロの導入も選択肢として広がっています。
導入後は長期間にわたって安定的に発電が見込まれ、エネルギーコストの抑制と環境負荷の低減の両立が期待できます。
さらに、蓄電池やV2H(電気自動車との連携設備)を組み合わせることで、夜間利用や非常用電源としての活用も可能になり、BCP(事業継続計画)対策としても有効です。
工場における省エネは、一度にすべてを取り組む必要はありません。
まずは契約内容の見直しなど手軽に始められることから着手し、段階的に再エネ設備の導入などへと広げていくことが現実的で効果的な進め方です。
経営の視点からも、エネルギーコストの最適化と持続可能な運用体制づくりは、今後ますます重要になっていくでしょう。
工場の省エネは、岡山電力にお任せください
電気代や燃料費の高騰、環境対応の必要性が高まる中、省エネルギーへの取り組みは工場経営にとって避けて通れないテーマとなっています。
照明や空調の見直しといった身近な対策から、太陽光発電の導入、電力契約の最適化まで、できることから一つずつ取り組んでいくことで、コスト削減と脱炭素の両立が実現できます。
岡山電力では、こうした省エネ対策の検討から導入、補助金の申請サポート、設備の施工・管理まで、一貫したご支援が可能です。
お客様の現場やご要望に合わせて、最適なプランをご提案いたします。
「まずは何から始めたらよいかわからない」「補助金を使えるか知りたい」といったご相談も歓迎しています。
エネルギーのことなら、ぜひ岡山電力へお気軽にご相談ください。