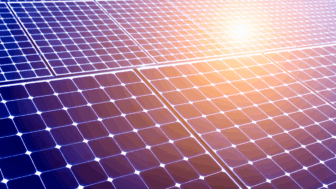工場の電気代は、事業規模や使用設備、稼働時間によって大きく変わります。
特に昨今は、電力単価の上昇により、これまで以上にエネルギーコストが経営に与える影響が大きくなっています。
以下は、一般的な中小規模工場と大規模工場における電気代の目安と、それぞれの特徴をまとめた一覧です。
| 区分 | 月間電気代の目安 | 従業員数の目安 | 坪数の目安 | 備考 |
| 中小規模工場 | 10万~100万円程度 | 約300人未満 | 約300~3,000坪 | 食品加工 印刷 小型金属加工 など |
| 大規模工場 | 100万円以上 | 約300人以上 | 約3,000坪~ | 自動車部品 鉄道の車両 エアコン など |
中小規模の工場では、比較的抑えた電気使用量で運営するケースが多いものの、照明や空調、加工機器などのエネルギー負荷が積み重なり、月間で数十万円の電気代が発生するのが一般的です。
一方、大規模工場では、設備の数や稼働時間が長くなるため、月に100万円を超える電気代がかかるケースも少なくありません。
これらのコストは固定費として毎月発生するため、経営への影響は大きく、省エネ対策や契約見直しによる改善が求められます。
ここでは、こうした電気代の削減に向けた具体的な対策をご紹介します。
工場の電気代の内訳と仕組みを理解しよう
工場の電気代を削減するためには、まずその内訳と計算の仕組みを正しく理解することが重要です。
毎月の電気料金には「基本料金」と「使用料金(従量料金)」という2つの大きな要素があり、契約内容や使用状況によって金額が大きく変動します。
ここでは、工場における電気代の構成について、2つのポイントに分けて解説します。
①基本料金と使用料金の違い
電気料金は、大きく分けて「基本料金」と「使用料金(従量料金)」で構成されています。
基本料金は、契約している電力の大きさ(kW)に応じて毎月固定で支払う金額です。
たとえ使用量が少ない月でも、契約している容量分の基本料金は発生します。
これは、電力会社がその容量を常に供給できるよう準備しているために発生する費用であり、主に高圧契約(工場や事業所)で設定されます。
一方、使用料金(従量料金)は、実際に使った電力量(kWh)に応じて変動する部分です。
月によって使用量が変わる場合、この使用料金の割合が大きくなります。
使用料金の単価は時間帯や契約プランによって異なり、「昼間が高く、夜間は安い」などの時間帯別単価が設定されていることもあります。
このように、基本料金=固定費、使用料金=変動費と捉えることで、電気料金の見直しや対策の優先順位が明確になります。
②契約電力・力率・料金単価の仕組み
工場における電気料金は、使用量だけでなく「契約電力」や「力率」といった技術的な要素にも影響を受けます。
まず、契約電力とは、工場で使用する最大電力のことです。
これは過去1年間のうち、最も電力使用量が多かった30分間の平均値をもとに決まります。
この数値が高いと、それに応じて基本料金も高くなる仕組みです。
したがって、短時間だけ大きな機器を一斉に動かすなどのピーク電力を抑えることが、基本料金削減のポイントになります。
次に、力率とは、電気をどれだけ効率的に使っているかを示す指標です。
工場では、モーターなどの機器によって無効電力が発生するため、力率が低くなる傾向があります。
力率が低下すると、契約によっては電気料金に「力率割引の対象外」や「割増料金」が発生する場合もあります。
対策としては、進相コンデンサの設置などで力率を改善する方法があります。
最後に、料金単価は契約プランごとに異なり、基本的には契約電力の大きさや電力の使用パターン(昼間中心か夜間中心か)によって設定されます。
複数の料金プランが存在する場合は、自社の使用状況に最も合ったプランを選ぶことで、電気代の見直しにつながります。
契約の見直しでコスト削減!チェックすべき3つのポイント
工場や事業所の電気代を削減するには、まず契約内容の見直しが効果的です。
設備の使用状況や時間帯、契約プランの内容によっては、今よりもコストを抑えられる可能性があります。
ここでは、電気料金の最適化に向けて確認したい3つのポイントを紹介します。
①電力会社の切り替え
2016年の電力自由化以降、電力会社の選択肢が広がりました。
従来の大手電力会社だけでなく、新電力(特定規模電気事業者)やPPA(第三者所有モデル)など、さまざまなサービス形態が提供されています。
新電力への切り替えによって、契約内容次第では従来の大手電力会社よりも基本料金や従量料金(使用量に応じた単価)が割安になるケースがあります。
たとえば、高圧電力契約では、基本料金が「最大需要電力(過去1年間で最も使用量が多かった30分間)」を基準に設定されていますが、新電力ではこの算定方法や単価が独自に設定されていることがあり、ピーク電力の発生が少ない工場では特に有利な料金体系になる可能性があります。
また、従量料金に関しても、時間帯別や季節別に変動する単価が柔軟に設計されている場合があり、使用パターンに合致すれば、実際の使用量は変わらなくても料金が下がることがあります。
さらに、新電力の中には、JEPX(日本卸電力取引所)の市場価格に連動した「市場連動型プラン」を提供している会社もあります。
このタイプのプランは、電力市場の価格変動に応じて料金単価が変わる仕組みで、市場価格が安定または低水準の時期には、大手電力会社の標準的な料金プランよりも電気代を大きく抑えられる可能性があります。
弊社でも、こうした市場価格に連動したプランを取り扱っており、特に昼間の電力使用量が多い工場や施設でコスト削減効果が高い傾向があります。
実際に、JEPX単価が比較的低く推移する時間帯を活用することで、従来の固定単価契約と比較して月間の電気料金を数万円以上削減できた事例もあります。
また、太陽光発電設備を第三者が設置し、その発電電力を利用するPPAモデルでは、初期費用なしで再エネを導入でき、長期的な電気代削減も期待できます。
選定の際は、契約内容の柔軟性や料金体系、供給実績などを総合的に比較検討することが大切です。
②契約電力の適正化とピークシフト
電気料金の中で大きな割合を占める「基本料金」は、契約電力(過去1年間の最大需要電力)に応じて設定されています。
そのため、短時間でも電力使用量が急増するタイミング(ピーク)があると、基本料金が高く設定されてしまうことがあります。
このような無駄を避けるためには、契約電力が実際の使用に合っているかを定期的に確認し、必要に応じて見直すことが重要です。
加えて、「ピークシフト」と呼ばれる対策、つまり使用の集中する時間帯をずらす運用の工夫によって、契約電力を抑えることも可能です。
たとえば、大型機器の起動時間を分散させたり、深夜や早朝の稼働を一部活用するなどの調整が考えられます。
③料金プランの選び方と見直し時期
工場や施設の電力使用状況に応じて、選ぶべき料金プランも異なります。
電力会社ごとに複数の料金メニューが用意されており、「時間帯別料金制」「季節別単価」などを活用することで、使用パターンに合ったプランを選べば料金の最適化につながります。
また、プランの見直しは定期的に行うことが望ましく、少なくとも1年に1回は使用実績をもとに再検討するのが理想です。
電気料金の単価が見直されるタイミングや、契約更新の時期に合わせて再評価することで、無駄なコストの発生を防ぐことができます。
工場の電気代対策4選
工場の電気代は、使用する設備や稼働時間、運用方法によって大きく変わります。
日々の運用の見直しや設備の最適化を進めることで、コスト削減とエネルギー効率の向上が期待できます。
ここでは、工場で実施しやすい4つの電気代対策をご紹介します。
省エネ対策①|空調と照明の電力使用を抑える
空調と照明は、工場の電気使用量の中でも大きな割合を占める設備です。
空調については、設定温度の適正化や使用時間の見直し、フィルターの定期清掃などによって消費電力を抑えることができます。
照明では、LED照明への切り替えや、人感センサー・タイマー制御の導入によって、必要な時間・場所だけで稼働させる工夫が有効です。
特別な設備投資をしなくても、ちょっとした改善で電力の使用効率を高められるため、比較的取り組みやすい対策のひとつです。
省エネ対策②|生産設備の更新とメンテナンス
生産設備が古くなっている場合、稼働効率の低下とともに余分な電力を消費している可能性があります。
高効率な設備への更新は、初期費用はかかるものの、長期的には電気代削減と安定稼働の両方に貢献します。
また、既存設備であっても、定期的なメンテナンスを行うことで性能を維持し、電力の無駄な消費を防ぐことができます。
機械の状態を把握し、適切に保つことも重要な省エネ対策のひとつです。
省エネ対策③|太陽光発電や蓄電池で昼間の電力をカバー
昼間の使用電力量が多い工場では、太陽光発電を導入することで自家消費型の電力供給が可能になります。
購入電力量を減らせるため、月々の電気代削減につながります。
さらに、蓄電池を組み合わせることで、夜間や非常時の電力確保も実現できます。
特に、ピーク時間帯の電力使用を抑える「ピークカット」効果が期待できるため、基本料金の抑制にもつながります。
補助金制度の活用も含めて、導入効果を丁寧に見極めることがポイントです。
省エネ対策④|電力の見える化で運用状況を把握する
工場では、日常的な業務の中で電力の使われ方を正確に把握することは難しい場合があります。
そこで、エネルギー管理システムを導入し、設備ごとの使用電力量や時間帯ごとの負荷状況を可視化することで、使用傾向をより明確に把握できるようになります。
こうした「見える化」により、電力使用量が多い時間帯や機器の特定が可能になり、稼働時間の見直しや不要な待機時間の削減など、運用の改善に役立てることができます。
継続的にデータを確認し、必要に応じて調整を行うことで、省エネルギー効果を高めていくことができます。
どの対策も、工場の現状に合わせて取り組むことで、無理のないコスト削減が期待できます。
まずはできるところから見直し、将来的には設備投資や再エネ導入なども視野に入れて、段階的に省エネを進めていくことが重要です。
電力会社の見直し×省エネで経営体質を強くする
電気代の上昇やエネルギーの使い方に対する関心の高まりを受け、工場や事業所では「電力コストの最適化」と「省エネの取り組み」が重要な経営課題となっています。
日々の運用を見直し、適切な対策を重ねることで、電気料金の削減だけでなく、事業の継続性や環境への配慮といった面でもプラスの効果が期待できます。
まずは、現在の電力契約が自社の使用状況に合っているかを確認し、必要に応じて電力会社の切り替えや料金プランの見直しを検討することが有効です。
さらに、省エネ対策として、空調・照明の効率化、生産設備の更新、太陽光発電の導入、電力の見える化など、段階的な取り組みを進めることで、無理のない形でコスト削減が可能になります。
岡山電力では、電力契約の最適化に関するご相談はもちろん、太陽光や蓄電池を含めたエネルギー全体の見直しにも対応しています。
事業規模や運用状況に応じて、最適なプランをご提案いたしますので、電気代の見直しや省エネの導入をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。