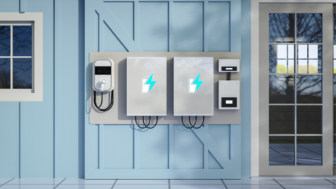2025年に入り、電気料金の値上げがますます現実のものとなっています。
燃料価格の高騰や再生可能エネルギー導入のコスト増加、送電網の維持費用の上昇など、さまざまな要因が電気料金に影響を与えており、家計や経済に大きな負担をもたらしています。
家庭においては、月々の電気代が上がることで生活費の圧迫につながり、特に冬場や夏場の冷暖房使用時には大幅な出費増加が懸念されています。
一方、企業においても電力コストの増加は製造業や小売業を中心に大きな影響を与え、商品の価格転嫁や経営コストの上昇といった経済全体のインフレ圧力につながる可能性があります。
ここでは、2025年の電気料金の値上げ幅や要因を詳しく解説するとともに、今後の電気料金の見通しや、電気代の上昇に対する具体的な対策について徹底解説します。
電気代の負担を抑えるための情報を知り、適切な対策を講じるために、ぜひ最後までご覧ください。
2025年の電気代値上げはどのくらい?いつから?地域別の影響
2025年の電気料金は、政府の補助金縮小や燃料価格の高騰を背景に、全国的に値上げが予定されています。
特に、2025年4月の検針分(3月使用分)から、大手電力会社10社すべてで電気料金の引き上げが実施される見込みです。
ここでは、各電力会社の値上げ状況や地域ごとの影響、過去10年間の電気料金の推移と今後の見通しについて詳しく解説します。
①大手電力会社の今後の値上げ一覧
以下は、2025年4月から予定されている大手電力会社の値上げ状況の一覧です。
大手電力会社 4月請求分の電気代 前月比 北海道電力 9,155円 +301円 東北電力 8,485円 +366円 東京電力 8,595円 +377円 中部電力 8,379円 +411円 北陸電力 7,406円 +294円 関西電力 7,326円 +312円 中国電力 8,103円 +346円 四国電力 8,197円 +333円 九州電力 7,223円 +302円 沖縄電力 9,232円 +375円
※平均的な使用量に基づく
参考「Yahoo!ニュース:電気とガス代、全社値上がり 3月使用分、補助金の縮小で」
4月の電気料金請求分では、補助額が半減し、10社が値上げを予定しているため、多くの家庭で電気料金の負担が増加する可能性があります。
②各電力会社の値上げ理由と影響
北海道電力(値上げ額+301円)
北海道電力は、経営基盤強化推進委員会のもと、コスト削減や経営効率化を進めていますが、燃料価格や卸電力市場価格の高騰、円安の進行により、電力供給コストが電気料金収入を上回る状況が続き、財務状況が悪化しています。
このため、2023年6月1日より規制料金および低圧自由料金の値上げを実施し、高圧・特別高圧の料金についても2023年4月1日より改定しました。
また、2024年12月に公表された貿易統計値に基づき、2025年3月分の電気料金に適用する燃料費調整単価が確定しました。
国の電気・ガス料金支援策により、2025年3月分の電気料金では、低圧供給で1kWhあたり2円50銭、高圧供給で1円30銭の値引きが適用されます。
参考「ほくでん:2025年3月分電気料金の燃料費等調整に関するお知らせについて」
東北電力(値上げ額+366円)
東北電力は、地震・台風などの災害時に被災されたお客さまへの電気料金の特別措置を特定小売供給約款に規定し、2025年4月1日より実施します。
従来は災害救助法が適用されるたびに認可手続きを経て特別措置を講じていましたが、国の審議会の方針を踏まえ、約款へ明文化することで迅速な対応が可能になりました。
また、2024年12月の貿易統計値に基づき、2025年3月分(2月使用分)の電気料金の燃料費調整単価が確定しました。
規制料金プランの低圧契約では、1kWhあたり▲9.78円(前月比+0.15円)となり、従量電灯の標準モデル(30A・260kWh使用)では、前月より39円上昇し8,119円となります。
自由料金プランの低圧契約では、1kWhあたり▲11.78円(前月比+0.15円)の調整単価が適用されます(国の電気料金特別措置および感謝割引を含む)。
参考「東北電力:2025年4月1日実施のご契約内容の見直しについて」
東京電力(値上げ額+377円)
2024年4月1日より、発電側課金制度の導入に伴い、託送料金が発電事業者向け(発電側料金)と小売電気事業者向け(需要側料金)に区分され、これに基づき託送料金の見直しが行われます。
この変更により、東京電力のすべての電気料金単価に託送料金の変動分を反映します。
託送料金の見直しに伴い、基本料金単価は上がり、電力量料金単価は下がるため、お客さまの使用状況によって電気料金への影響額が異なります。
この変更は、各エリアの一般送配電事業者による託送料金の改定を受けたものであり、2024年4月1日から適用されます。
中部電力(値上げ額+411円)
2024年11月〜2025年1月の平均燃料価格が確定したことに伴い、2025年4月分の電気料金に適用される燃料費調整が決定されました。
これにより、低圧供給は1kWhあたり1円30銭、高圧供給は0円70銭の値引きが適用されます。
また、政府の経済対策による電気料金の支援措置に加え、当社の負担軽減策として、2025年4月から2026年3月までの期間、高圧・特別高圧供給のお客さまに対し、燃料費調整単価を1kWhあたり1円00銭値引きすることといたしました。
なお、2025年2月および3月分の電気料金では、低圧供給で1kWhあたり2円50銭、高圧供給で1円30銭の値引きが実施されていました。
参考「中部電力ミライズ:2025年4月分電気料金の燃料費調整について」
北陸電力(値上げ額+294円)
北陸電力は、すべての電気料金について改定を実施することとなりました。
規制料金メニュー(ご家庭・商店・工場など)については、2022年11月30日に経済産業大臣へ認可申請を行い、国の審査を経て2023年5月19日に認可を受け、2023年6月1日より料金改定を実施しました。
自由料金メニュー(オール電化住宅・商店・工場など)については、2023年7月以降、燃料費調整単価の算定方法を規制料金と統一し、一部のメニュー(従量電灯ネクスト・節電とくとく電灯・低圧電力ネクスト)の料金単価も規制料金の認可内容を踏まえた見直しを実施します。
関西電力(値上げ額+312円)
関西電力は、2024年8月〜10月の燃料価格公表を受け、2025年1月分の電気料金に適用される燃料費調整単価を発表しました。
低圧契約(従量電灯A・B、低圧電力等)の燃料費調整単価は+2円24銭/kWhで、前月(2024年12月分)と同額となります。
一方、はぴeタイムRや時間帯別電灯などの選択約款を適用している契約では+3円70銭/kWhとなり、前月より0円16銭の値下げとなります。
燃料費調整単価は基準燃料価格(27,100円/kl)と平均燃料価格の差額をもとに算定されますが、今回の調整では平均燃料価格が上限(40,700円/kl)を超えたため、この上限価格を適用しています。
中国電力(値上げ額+346円)
2024年11月の貿易統計が発表され、2024年9月〜11月の平均燃料価格が確定したことに伴い、2025年2月分の電気料金に適用される燃料費等調整単価が決定しました。
低圧供給のお客さま向けの燃料費調整単価は、1kWhあたり▲8.67円となり、前月と同額です。
また、「電気・ガス料金支援」による特別措置が適用されることで、最終的な燃料費等調整単価は▲11.17円/kWhとなります。
この調整により、標準的な家庭(従量電灯A・260kWh使用)では、2月分の電気料金が前月より650円安い7,721円、600kWh使用する家庭では1,500円の値下げで18,318円となる見込みです。
特別措置が適用されることで、一時的に電気料金の負担軽減が期待できますが、今後の燃料価格や補助金の動向によってはさらなる変動が予想されます。
参考「中国電力:2025 年 2 月分電気料金の燃料費等調整について」
四国電力(値上げ額+333円)
2024年12月の貿易統計発表に伴い、2025年3月分の電気料金に適用される燃料費調整単価が確定しました。
平均燃料価格の変動により、燃料費調整単価は低圧供給で▲8円51銭/kWh、高圧供給で調整が適用されます。
政府の「電気・ガス料金支援」により、2025年2月~3月分の電気料金は低圧で2.5円/kWh、高圧で1.3円/kWh、4月分は低圧で1.3円/kWh、高圧で0.7円/kWhの割引が適用されます。
2025年3月分の標準的な家庭(260kWh使用)の電気料金は7,864円となり、政府の負担軽減措置により650円の割引が適用されています。
今後も燃料価格や政府の支援策の動向によって、電気料金の変動が予想されます。
参考「四国電力:2025年3月分電気料金の燃料費調整について」
九州電力(値上げ額+302円)
2025年4月1日より、低圧の一部料金プラン(旧オール電化メニュー等)について電気料金の見直しを実施します。
これは、再生可能エネルギーの導入拡大や電力需要の変化に対応し、安定的な電力供給を維持するための措置です。
また、2025年4月分の電気料金に適用される燃料費調整単価が確定しました。
2025年2月分(1月使用分)からは国の「電気・ガス料金支援」による割引が反映され、低圧で2.50円/kWh、高圧で1.30円/kWhの割引が適用されています。
4月分からは、低圧1.30円/kWh、高圧0.70円/kWhへと縮小される予定です。
さらに、2025年4月以降の契約更新に合わせ、高圧・特別高圧のお客さま向けに市場価格調整の見直しを順次適用します。
参考「九州電力:低圧の一部のお客さまの電気料金の見直しを実施します(主に旧オール電化メニューのお客さま)」
沖縄電力(値上げ額+375円)
2024年10月〜12月の平均燃料価格が確定し、2025年3月分の電気料金に適用される燃料費調整単価が決定しました。
平均燃料価格は81,500円/kl、離島平均燃料価格は79,300円/klで、これに基づき燃料費調整が行われます。
2025年2月分と比べ、2025年3月分の燃料費調整単価は低圧で▲2.5円/kWh、高圧で▲1.3円/kWhの値引きが適用され、低圧供給のお客様の電気料金は約44円の値上がりとなります。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は907円で、国の電気料金支援による割引(低圧:2.5円/kWh、高圧1.3円/kWh)も反映されます。
最終的に、2025年3月分の電気料金はお支払額が8,813円となり、電気料金の負担が軽減されることが期待されます。
参考「沖縄電力:2025年3月分電気料金の燃料費等調整について」
2025年の電気代はなぜ値上がりするの?4つの要因を解説
2025年に電気料金が値上がりする主な原因には、燃料価格の高騰、再生可能エネルギー賦課金の増加、送配電コストの上昇、円安と国際情勢の影響が挙げられます。
これらの要因が相まって、家庭や企業の電気料金に大きな影響を与えることが予想されています。
ここでは、これらの要因が電気料金にどのように影響するのかを詳しく解説します。
要因①燃料価格の上昇(LNG・石炭・原油の高騰)
電力の多くはLNG(液化天然ガス)、石炭、原油などの化石燃料を使って発電されています。
近年、これらの燃料価格は世界的に高騰しており、特にLNGの価格が大きく上昇しています。
- LNGの価格上昇
液化天然ガスの需要が増加し、供給が追いつかない状況が続いています。
そのため、LNGの価格が高騰しており、発電コストが上昇しています。 - 石炭と原油の価格上昇
石炭や原油も発電に使われているため、これらの価格の高騰が直接的に電力の調達コストを押し上げています。
これにより、発電所が購入する燃料コストが増加し、そのコストが電気料金に反映される形となります。
要因②再生可能エネルギー賦課金の増加(FIT・FIP制度の影響)
日本では、再生可能エネルギーの導入を進めるためにFIT(固定価格買取制度)やFIP(市場連動型買取制度)が導入されています。
これらの制度は、太陽光発電や風力発電の価格保証を行い、再生可能エネルギーの導入を促進するものです。
- FIT制度の影響
再生可能エネルギーの導入を支援するために、電力会社が太陽光や風力などの発電設備に対して高価格で電力を買い取る義務を負っています。
このコストは電力料金に上乗せされる形で、消費者に転嫁されます。 - FIP制度の影響
市場連動型買取制度(FIP)も、再生可能エネルギーの導入を促進するために存在しますが、これに伴うコスト増加が電気料金に影響を与えています。
これらの制度によって、再生可能エネルギーの導入が進む一方で、そのコストを負担するための賦課金が増加し、電気料金が値上がりする原因となっています。
要因③送配電コストの上昇と電力インフラ維持費の増加
電気を家庭や企業に届けるためには、送電網と配電網の維持・運用が必要です。
これらのインフラの維持費が高騰していることも電気代の値上げに繋がっています。
- 送配電コストの上昇
送電線や配電線の老朽化に伴い、インフラの修繕や更新にかかる費用が増加しています。
また、自然災害による影響や予防策として、インフラの強化に対する投資が必要です。 - 電力インフラ維持費の増加
電力網の維持には高額な費用がかかるため、これらのコストは最終的に消費者に転嫁されることになります。
これらのコスト上昇は、電力会社の負担となり、最終的には電気料金の値上げとなって顕在化します。
要因④円安・国際情勢の影響でエネルギー調達コストが増加
日本はエネルギー資源を輸入に頼っており、円安や国際情勢の影響を受けやすい国です。
特に、エネルギー価格が国際市場で変動することが電気料金に直接影響を与えています。
- 円安の影響
円安が進行すると、外国から輸入するエネルギー資源(LNG、原油、石炭など)の価格が高くなり、そのコストが電力料金に反映されます。 - 国際情勢の影響
戦争や貿易摩擦など、国際情勢の不安定さがエネルギー供給に影響を与え、価格が急激に変動することがあります。
これがエネルギー調達コストの増加につながります。
これらの外的要因は、日本の電力供給に大きな影響を与え、結果として電気料金の値上がりを招く原因となっています。
2025年の電気代値上げに対応する政府補助金情報
2025年、電気料金の値上げが家計や企業に大きな影響を与える中、政府は電気代負担軽減のための支援策を実施しています。
特に、2025年1月から3月までの間に実施される補助金により、一定の負担軽減が期待されていますが、3月以降の補助金の見通しについても注目が集まっています。
①電気代負担軽減のための政府の支援策
政府は、2025年1月から3月までの間、電気代負担軽減のための支援策として、燃料費調整の割引を実施しています。
この期間中は、低圧供給のお客さまに対して1kWhあたり2.5円、高圧供給のお客さまには1kWhあたり1.3円の割引が適用されます。
補助金の内容
- 期間:2025年1月~3月までの電気料金
- 低圧供給のお客さま:1kWhあたり2.5円の割引
- 高圧供給のお客さま:1kWhあたり1.3円の割引
これにより、電気使用量に応じた割引が適用され、特に電力消費の多い家庭や企業にとって大きな支援となります。
たとえば、月間電力使用量が300kWhの場合、低圧供給では月額750円の割引が得られます。
②3月以降の補助金の見通し
2025年3月以降については、補助金の適用が縮小される見込みです。
特に、3月分の電気料金には、補助額が減額される予定であり、4月分からは補助金が終了する可能性もあります。
2025年3月以降の見通し
- 2025年3月分:低圧供給の補助額は1kWhあたり2.5円から1.3円に縮小
- 2025年4月以降:補助金終了の可能性が高く、電気料金の負担が再び増加する見込み
政府は、2025年3月以降、燃料費調整単価を軽減する措置を実施しているものの、電気料金の上昇が続く可能性があるため、省エネ対策や太陽光発電の導入など、長期的な節約策を検討することが重要です。
2025年の電気代値上げに備えて今すぐできる節約対策3選
2025年に向けて、電気代の値上げが続く見込みであり、家庭や企業の負担が大きくなっています。
今後の電気料金上昇に備えて、今すぐできる節約対策を講じることが重要です。
ここでは、電気代の値上げに備えて今すぐできる節約対策を詳しく解説します。
対策①契約している電力会社の料金プランを見直す
電気料金を削減するための最も基本的な方法は、現在契約している電力会社の料金プランを見直し、自分のライフスタイルに最適なプランを選ぶことです。
電力プランの見直しで電気代を削減
- 電力使用時間帯に合わせたプランを選ぶ
昼間の電力消費が多い家庭は昼間の電気料金が安いプラン、夜間に電気を多く使うオール電化家庭は夜間の電力単価が安いプランを選ぶことでコストを抑えられます。 - 電力会社を切り替える
地域の電力会社よりも新電力会社の方が安いプランを提供している場合があるため、複数の電力会社を比較してみるのも有効です。 - セット割やポイント還元を活用する
ガスとセットで契約すると割引が受けられるプランや、電気代の一部がポイント還元されるサービスを活用することで、実質的な負担を減らすことができます。
定期的に契約プランを見直し、自分に合った料金プランを選ぶことで、毎月の電気代を抑えることが可能です。
対策②省エネ家電やエコキュート導入でさらに電気代を削減
電気代を削減するためには、使用する電力量そのものを減らすことも重要です。
そのため、省エネ性能の高い家電を導入し、無駄な電力消費を抑えることが有効な対策になります。
省エネ家電を活用するメリット
- LED照明の導入
白熱電球に比べて消費電力が約80%削減できるため、照明の電気代を抑えることが可能。 - 高効率エアコンの使用
最新の省エネ型エアコンは、従来モデルに比べて電気代を抑えながら快適な温度調整が可能。 - インバーター搭載家電の活用
冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどのインバーター制御機能付き家電を選ぶことで、電力の消費量を最適化できる。
また、オール電化住宅の家庭では「エコキュート」の導入も有効です。
エコキュートは夜間の安い電力でお湯を沸かし、昼間に使用することで電気代を削減する仕組みになっており、特に電力消費が多い家庭におすすめです。
省エネ家電やエコキュートの導入により、長期的に電気代を削減し、エネルギー効率の良い生活を実現することが可能です。
対策③太陽光発電や蓄電池の導入で長期的に対策
電気料金の上昇に対抗するための最も効果的な方法の一つが、太陽光発電と蓄電池を活用し、自家消費を増やすことです。
太陽光発電のメリット
- 日中の電力を自家発電でまかなうことで、電力会社からの買電量を削減できる
- 余剰電力を売電することで、電気代の負担を軽減できる
- 再生可能エネルギーを活用することで、環境負荷を軽減できる
蓄電池を導入するメリット
- 昼間の余剰電力を蓄えて夜間に使用することで、買電量をさらに削減できる
- 電力料金が安い深夜に充電し、昼間に使用することでコストを最適化できる
- 停電時にも電力を確保できるため、防災対策としても有効
特に、太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、電力会社に頼らない「エネルギー自給自足型」の生活を実現することが可能になります。
電気代削減シミュレーション
項目 太陽光発電なし 太陽光発電あり(5kW) 太陽光+蓄電池(10kWh) 年間電気代 約15万円 約9万円 約5万円 年間電気代削減額 なし 約6万円 約10万円
このように、太陽光発電と蓄電池を活用することで、年間約10万円の電気代削減が可能になります。
自家消費を増やすことで電気代の上昇リスクを抑えることができるため、長期的な対策として非常に有効です。
2025年の電気代値上げに関するご相談は岡山電力まで!
2025年の電気代値上げは、燃料価格の高騰や送配電コストの増加、再生可能エネルギー賦課金の増加など、さまざまな要因により実施されることが予想されます。
これにより、家庭や企業の電気代負担が大きくなることが懸念されています。
しかし、適切な対策を講じることで、電気代の節約が可能です。
特に、省エネ家電の導入や時間帯別料金プランの活用、太陽光発電や蓄電池の導入が、長期的に電気代削減に貢献する方法であることがわかりました。
岡山電力では、お客様に最適な電力プランや電気代削減のアドバイスを提供し、電気代の値上げに備えるための具体的な対策をサポートしています。
「電気料金が値上がりしそうで不安」「今の電力プランが自分に合っているのか知りたい」「省エネ対策や太陽光発電の導入について相談したい」など、電気代に関するお悩みがあれば、ぜひ岡山電力にご相談ください。
最適なプランをご提案し、電気代の負担軽減に向けてしっかりサポートさせていただきます。