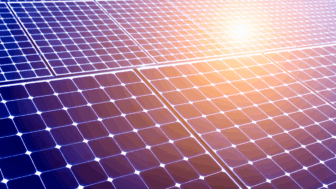近年、再生可能エネルギーの普及が進むなかで、多くの家庭が太陽光発電の導入を検討しています。
特に、政府のFIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を促進する重要な仕組みとして注目されています。
この制度を活用すれば、発電した電気を一定の価格で売電でき、設置コストの回収がしやすくなる可能性も。
しかし、FIT制度には適用期間があり、一定年数が経過すると「卒FIT」を迎えます。
卒FIT後は、売電価格が大幅に下がるため、事前に考えておくことが重要です。
FITを活用した自家消費の拡大や、電力会社との新たな売電契約、電力シェアリングといった選択肢をあらかじめ用意しておくことにより、長期的な電力活用の計画が立てやすくなります。
この記事では、FIT制度の仕組みやメリットに加え、卒FIT後の対策や、初期費用を抑える肝心な方法について詳しく解説します。
太陽光発電を検討している方にとって、将来的なエネルギー活用を考えるヒントがたくさんあるので、ぜひ参考にしてください!
FIT制度の概要と目的
ここでは、FIT制度の概要と目的について解説していきます。
それぞれ、確認していきましょう。
FIT制度とは「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」
FIT制度(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーによる発電を促進するために、日本政府が2012年に導入した制度です。
正式名称は「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(固定価格買取制度: FIT)」で、再生可能エネルギーによる電気を一定の価格で、一定期間、電力会社が買うことを義務付けています。
この制度の導入により、一般家庭や企業が太陽光発電や風力発電などの再生可能なエネルギー設備を導入しやすくなり、長期的な収益を見込む仕組みが準備されました。
発電方法は、以下の5つです。
- 太陽光発電
- 風力発電
- 水力発電
- 地熱発電
- バイオマス発電
これらの発電設備を設置した家庭や事業者は、電力会社へ売電し、固定価格での買取を受けることができます。
FIT制度の目的
FIT制度の最大の目的は、「再生可能エネルギーの普及促進」です。
日本のエネルギー自給率は低く、電力の多くを海外からの輸入燃料に依存している現状があります。
変動やリスクに左右されるため、安定したエネルギー供給を確保するためにも、国内での再生可能エネルギーの活用が重要視されています。
FIT制度の導入によって得られる主な特典は、以下のとおりです。
- 再生可能エネルギーの普及促進
太陽光発電や風力発電の導入を後押しし、クリーンエネルギーの利用を拡大する。 - エネルギーの安定供給
国内での再生可能エネルギーの生産を増加し、海外へのエネルギー依存度を軽減する。 - 環境負荷の低減
再生可能エネルギーは、地球発電時にCO2を排出しないため、温暖化対策にも貢献する。
FIT制度の背景
FIT制度が導入された背景には、エネルギー問題と環境問題の両方があります。
日本のエネルギー自給率は約13.3%(2021年度見通し)と、OECD加盟国のなかでも特に低い水準です。
そのため、石油・天然ガス・石炭といった化石燃料の輸入に大きく依存しており、原油価格のあるいは地政学的なリスク(戦争や紛争)により、電力コストが大きく変動する問題があります。
また、日本の発電電力量の約72.8%は発熱発電によって賄われており、大量のCO2が排出されています。
このような状況を改善するために、政府は再生可能エネルギーの導入を促進する政策としてFIT制度を導入しました。
FIT制度の仕組み
ここでは、FIT制度の仕組みについて解説していきます。
それぞれ、確認していきましょう。
FIT制度を支える賦課金とは?
FIT制度では、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の価格で買いとりますが、その購入費用は「再生可能エネルギー発電促進賦課金(有料)」として電気利用者が負担しています。
賦課金は、毎月の電気料金に上乗せされ、全国一律の上限が設定される仕組みです。
2024年度の賦課金は、1kWhあたり3.49円で、一般家庭の平均使用量(300kWh/月)では毎月約1,047円を支払うことになります。
再生可能エネルギーの普及を支援するため重要な制度ですが、FIT制度の買取価格が安くなり、賦課金の負担が増加している点には、注意が必要です。
今後、FIT制度の見直しや、新たな電力供給システム(FIP認証や電力シェアリング)への移行が進むと予想されており、消費者にとっても制度の取り組みを注視することが重要です。
一般家庭におけるFIT制度の適用
FIT制度は、個人が設置した太陽光発電システムにも適用されます。
例えば、家庭で発電した電力のうち、自家消費しきれずに余った電気は電力会社に売ることが可能です。
FIT制度の適用条件
- 10kW未満の太陽光発電システムを設置した一般家庭
- FIT認定を受けている設備であること
- 電力会社と売電契約を結ぶこと
特に、10kW未満の住宅用太陽光発電の場合、FIT制度の適用期間は10年間と定められています。
その期間内は、固定された価格で電気を売ることができ、安定した収入が得られるメリットがあります。
また、買取価格は年々変動しており、政府の方針により段階的に検討されています。
例えば、2024年度のFIT買取価格は1kWhあたり16円ですが、2025年度には15円まで検討される予定です。
FIT制度を利用するための必要手続き
一般家庭がFIT制度を利用するには、いくつかの手続きが必要です。
1. FIT認定の取得
まず、経済産業省の「再生可能エネルギー特別措置法」に基づき、FIT認定を取得する必要があります。
認定を受けることで、設置した太陽光発電システムがFIT制度の対象となり、売電が可能になります。
2.電力会社との接続契約
次に、発電した電気を動かすための電力会社との接続契約(系統連系契約)を結びます。
この契約により、電力会社は一定期間、定められた価格で電気を買う義務が発生します。
3. 売電開始
FIT認定と接続契約が完了したら、売電を開始できます。
発電した電力のうち、自家消費しきれなかった分が電力会社へ送られ、売電収入として毎月支払われます。
このように、FIT制度を利用するには事前の申請や契約が必要ですが、施工業者や電力会社が手続きをする代行ケースも多いため、個人での負担はそこまで大きくありません。
卒FIT後の概要と対策
ここでは、卒FIT後の概要と対策について解説していきます。
それぞれ、確認していきましょう。
卒FITとは何か?
FIT制度には、適用期間が設けられており、太陽光発電の出力が10kW未満の家庭用システムの場合、その期間は10年間と定められています。
この適用期間が終了することを「卒 FIT」と呼びます。
卒FITの仕組み
- FIT適用期間(10年間)が終了すると、固定価格での売電ができなくなる
- それまでの高い買取価格が適用されなくなり、売電上限が大幅に下がる
- 新たに電力会社と契約を結び、自由市場価格で売電することになる
FIT制度は2012年に導入されたため、2019年から順次卒FITを迎える家庭が増えてきています。
2024年時点では、2014年にFITを開始した家庭が卒FITの対象になります。
卒FITによるデメリットとリスク
卒FITを迎えた場合、以下のような扱いやリスクが生じます。
①売電価格の大幅な下落
FIT期間中は、例えば1kWhあたり16円(2024年度)で電力を売ることができますが、卒FIT後は8~10円程度に下がるケースが一般的です。
このため、これまで得られていた売電収入が大きく減少します。
②売電契約の再交渉が必要
FIT期間終了後は、電力会社と新たな契約を結ぶ必要があります。
③電気の自給自足が求められる
売電収入の減少により、従来通りの売電を続けるよりも、発電した電力を自家消費する方が経済的に有利になるケースがあります。
その場合は、蓄電池の導入や電気の有効活用が重要になります。
卒FIT後の余剰電力の活用方法
卒FITを迎えた後も、発電した電力を無駄にせず活用することが重要です。
主な方法として、以下の3つの対策があります。
①自家消費を促進する機器を導入
発電した電力をほとんど自宅で使うことが、最も経済的に有利です。
具体的な方法としては、以下のような機器の導入が挙げられます。
- 蓄電池の導入
夜間に発電した電気を夜間に使うことで、電気代を削減できる。 - EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)の充電
太陽光発電の電気をEVに充電し、夜間や外出時に活用できる。 - エコキュート(電気給湯器)の
太陽光の電気を使ってお湯を沸かし、効率的にエネルギーを利用できる。
② V2Hを導入する
V2H(Vehicle to Home)は、EV(電気自動車)に蓄えた電力を利用するシステムです。
卒FIT後に、EVのバッテリーを蓄電池の代わりに家庭で活用することで、電気の自給自足がより効率的になります。
EVのバッテリーは、一般的な家庭用蓄電池よりも容量が大きいため、緊急時の備えとしても有効です。
③地域や企業との電力シェアリングの可能性
近年、「P2P電力取引」や「電力シェアリング」のような仕組みが注目されています。
卒FIT後の電力を、個人間や地域で売買する仕組みを活用することで、新たな収益化が可能になる可能性があります。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
- ブロックチェーン技術を活用した電力取引
- 地域の電力共同利用プロジェクト
- 企業向けに直接電力を売る「コーポレートPPA」
これらの取り組みはまだ発展途上ですが、今後の電力市場自由化に伴って、卒FIT後の選択肢として広がる可能性があります。
太陽光発電を検討するときにFIT制度の理解が必要な理由
太陽光発電を導入するとき、FIT制度の仕組みやメリットを押さえておくことは、とても重要です。
FIT制度は、設置コストの回収を支援する仕組みとして機能しますが、将来的な「卒FIT」を見据えた計画も必要になります。
FIT制度の知識を活用した計画的な家計設計
太陽光発電を導入するとき、多くの家庭が気にするのが設置コストと回収期間です。
FIT制度を活用することで、売電収入を稼ぎながら初期投資を回収できます。
FIT制度では、一定期間を固定価格によって電力を売れるため、収益の見通しを立てやすくなります。
例えば、2024年度のFIT価格(16円/kWh)をベースに、年間発電量を4,500kWhと仮定すると、以下のようになります。
- 売電収入 = 4,500kWh × 16円 = 72,000円/年
- 10年間の総売電収入 =約72万円
この金額を考慮することで、初期投資額をどれくらいで回収できるのかを計算し、無理のない資金計画を立てることができます。
また、卒FIT後は売電上限が大きく下がるため、売電依存の収益構造にせず、あくまで自家消費を増やす対策が重要です。
例えば、卒FIT後の売電価格を8円/kWhと仮定すると、売電収入は半減し、10年以降の収益モデルは大きく変わります。
そのため、卒FIT後の対策として、以下のような計画を準備しておくと良いでしょう。
- 蓄電池の導入
- EV充電への活用
- 電力シェアリングの検討
太陽光発電の初期費用を抑える方法
太陽光発電の導入には、高価な初期費用がかかるため、コストを考慮した方法を活用することが重要です。
主な対策として、以下の3つが挙げられます。
①リース・PPAモデルの活用
最近では、初期費用0円で導入できるリース契約やPPA(電力購入契約)が普及しています。
リースでは、月額料金を支払いながら設備を利用でき、PPAでは発電した電気を最近の価格で購入するため、初期投資なしで太陽光発電を導入可能です。
②自治体の補助金を活用
多くの自治体が、太陽光発電や蓄電池の導入に補助金を提供しています。
例えば、東京都では蓄電池に最大70万円の補助があり、自治体によっては設備費用の一部がカバーされるため、設置コストを抑えられます。
③太陽光発電+蓄電池のセット契約
FIT終了後を見据え、太陽光発電と蓄電池をセットで導入する計画も増えています。
これにより、売電と自家消費のバランスを最適化して、電気代の削減や災害時の電源確保が可能となります。
これらの方法を活用すれば、無理のない資金計画で太陽光発電を導入できるでしょう。
まとめ
FIT(固定価格買取制度)は、再生可能エネルギーの普及を促進するために導入された制度であり、太陽光発電を設置する家庭にとって重要な仕組みです。
一定期間、固定価格で売電できるため、先行コストの回収を見るとメリットがあります。
しかし、FIT制度には適用期間があるため、卒FIT後の対策も考慮する必要があります。
売電価格の低下を見据え、自家消費を促進する設備(蓄電池やV2H)の導入や、電力シェアリングの活用を検討することが重要です。
また、太陽光発電を導入するときには、補助金やリース、PPAモデルを活用して初期費用を考えるなど工夫することで、経済的な負担を軽減できます。
エネルギー市場は、さらに変化することが予想されるため、FIT制度の仕組みや卒FIT後の選択肢を考え、自分に合った電力活用方法を選ぶことが大切です。
検討するときは、長期的な視点でメリットとリスクを念頭に置き、計画的な導入を進めましょう。