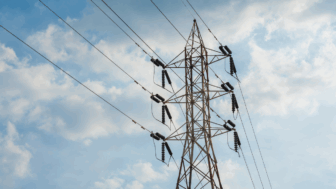太陽光発電を導入したけれど、卒FIT後の余剰電力ってどうなるの?そんな不安を抱えていませんか?
「余った電気は捨てるしかないのでは…」と心配している方も多いかもしれません。
しかし実際には、電気は捨てることができないエネルギーです。卒FIT後も、あなたの大切な発電電力を有効に活用する方法が数多く存在します。
この記事では、太陽光発電の余剰電力の仕組みから、卒FIT後に選べる具体的な4つの選択肢、自家消費や新しい電力取引の可能性まで、わかりやすく解説していきます。
読んだ後には、あなたにぴったりの「余剰電力の賢い使い方」がきっと見つかるはずです。
ぜひ最後までチェックしてください!
太陽光発電の余剰電力って捨てられるの?
太陽光発電システムを設置している家庭では、日中に発電して使いきれなかった電気、いわゆる「余剰電力」が発生します。
この余剰電力について、「使い道がなければ捨てられてしまうのでは?」と心配する声も聞かれます。
しかし、結論から言うと、電気は物理的に「捨てる」ことはできません。
電気はエネルギーであり、貯める・使う・売るといった方法でしか処理できないからです。
そのため、適切な方法で活用しなければ、せっかくの電力資源が無駄になってしまうことになります。
太陽光発電の余剰電力について
太陽光発電システムでは、自宅で使用する電力が優先的に供給され、使用量を超えて発電された分が余剰電力として扱われます。
この余剰電力は、電力会社に売電することが可能です。
住宅用太陽光発電(10kW未満)では、「余剰電力買取制度」によって、契約先の電力会社に一定期間、一定価格で買い取ってもらえます。
自家消費と売電のバランスをうまく取りながら、太陽光発電の恩恵を最大化することが重要です。
FIT制度とは?終了後に何が起きるのか
FIT(固定価格買取制度)とは、発電された電気を国が定めた価格で一定期間買いとることを保証する制度のことで、日本では2009年にスタートし、太陽光発電の普及を大きく後押ししました。
FIT期間は通常10年間であり、この期間中は安定した収入が得られるメリットがあります。
しかし、10年が経過するとFITは終了し、高価格での買いとりはおこなわれなくなります。
卒FIT後は、電力会社ごとに異なる条件での売電か、自家消費への切り替えが必要になります。
このタイミングでの適切な選択が、太陽光発電ライフをさらに豊かにするカギになります。
卒FIT後に選べる4つの選択肢
卒FIT後、太陽光発電で生まれた余剰電力をどう活用するかは大きなテーマです。
従来のように高単価で売電できなくなる一方で、新たな選択肢も生まれています。
ここでは、卒FIT後に選べる4つの具体的な選択肢を紹介します。
それぞれの特徴を把握し、あなたに最も合った方法を選びましょう。
①同じ電力会社と再契約して売電を継続する
卒FIT後、もっとも手軽でスムーズな方法は、これまで契約してきた電力会社と再度売電契約を結び、売電を継続することです。
多くの大手電力会社では、卒FIT専用の売電プランを用意しており、単価は7円〜9円/kWh程度に設定されています。
手続きもとてもシンプルで、追加の設備投資は不要なケースがほとんどです。
ただし、FIT期間中と比べると売電価格が大きく下がるため、売電収益は大幅に減少する点に注意が必要です。
煩雑な手続きを避けたい、または信頼できる既存の電力会社と引き続き取引したい場合には、現実的な選択肢と言えるでしょう。
②高く買ってくれる電力会社へ乗り換える
より高い収益を目指すなら、現在の電力会社にこだわらず、高価格で買い取ってくれる別の電力会社へ乗り換える方法があります。
新電力会社のなかには、卒FITユーザー向けに10円〜12円/kWhといった比較的高い買取価格を提示しているところもあり、さらに契約者向けに地域特産品のプレゼントやポイント還元キャンペーンなど、さまざまな特典を提供しているケースも見られます。
ただし、新規契約の手続きが必要になるほか、「電気の購入契約も同時に結ぶこと」が条件となっている場合もあるため、事前に詳細な契約内容をよく確認することが重要です。
売電価格だけでなく、総合的なメリットを比較しながら、最適な電力会社を選びましょう。
③自家消費する
売電による収益を期待するよりも、自宅で発電した電力をできる限り使い切る「自家消費」という選択もあります。
この方法では、発電した電気を直接家庭で使用するだけでなく、蓄電池を導入することで昼間に発電した電力を夜間に回して使うことも可能になります。
エコキュートを併用すれば、夜間の割安な電力を活用して効率的にお湯を沸かすことができ、光熱費全体の削減にもつながります。
初期投資として蓄電池やエコキュートの導入費用がかかるものの、電気代を大幅に節約できるうえ、災害時の非常用電源としても役立つため、長期的な安心感を得られる選択肢となるでしょう。
④地域新電力やP2P取引などの新しい選択肢を選ぶ
近年では、従来の売電とは異なる新たな選択肢も登場しています。
たとえば、地域新電力を利用すれば、地元で発電した電気を地域内で消費するという形で、地域経済への貢献を果たしながら売電が可能です。
また、P2P(個人間取引)型の電力取引では、ブロックチェーン技術を活用し、個人が発電した電力を別の個人に直接売買する仕組みが少しずつ普及し始めています。
これらの新しい仕組みはまだ発展途上ではあるものの、将来的に大きな可能性を秘めており、時代の先端を行く選択肢を求める人にとっては、とても魅力的な方法です。
地域密着型の電力会社や新たなプラットフォームを活用することで、売電だけでなく新しいライフスタイルを築くことができるでしょう。
太陽光発電の余剰電力を捨てることなく上手に使う方法
卒FITを迎えた今、発電した余剰電力をいかに無駄なく賢く活用するかが、太陽光発電ライフを充実させるポイントです。
これから紹介する方法を参考に、あなたにとって最適な電力活用スタイルを見つけましょう。
「太陽光発電の余剰電力」将来的に社会全体でどう活用される?
現在、個人宅レベルの話に留まらず、社会全体でも余剰電力を有効活用する動きが広がっています。
特に注目されているのが、電力を地域で循環させる「地域マイクログリッド」の構想です。
地域内で発電された電力を、地域内の需要に応じて配分する仕組みであり、エネルギーの地産地消を実現します。
また、EV(電気自動車)と連携させる「V2G(Vehicle to Grid)」の技術も進んでおり、家庭用蓄電池やEVが地域全体の電力安定化に寄与する未来も近づいています。
余剰電力が無駄になるどころか、社会全体のエネルギー効率向上に役立つ日も遠くないでしょう。
電力会社が余剰電力をどのように予測・調整しているか
電気は、基本的に貯めておくことが難しいエネルギーのため、電力会社は日々、電力の「需要と供給」のバランスを取るために精密な予測と調整をおこなっています。
例えば、日本気象協会の「日射量・発電量予測データ」や「電力需要予測データ」などを活用し、過去の消費パターンや気象データから、時間ごとの発電量と消費量をリアルタイムで予測しています。
予測に基づき、発電所の出力を増減させたり、場合によっては需要を抑えるための呼びかけをおこなったりしています。
卒FITによる小規模な余剰電力も、こうした全体の需給バランスの中で管理されており、「電力は捨てられない」という大原則のもとで、できる限り無駄なく社会に供給されているのです。
海外の事例に学ぶ日本の可能性
海外では、余剰電力の扱いについてさらに先進的な取り組みがおこなわれています。
例えばドイツでは、風力発電が盛んなため、予想以上に余剰電力が発生することがあります。
この余剰電力を国内だけで消費するのではなく、ヨーロッパ全体の送電網(メッシュグリッド)を通じて、隣国に電力を輸出する仕組みを整えています。
これにより、国内の供給過剰リスクを回避しつつ、発電した電力を有効活用しているのです。
日本でも、地域間連携の強化や国際送電網の検討が進められており、将来的にはこうした国境を越えた電力取引が現実になる可能性があります。
卒FIT後の余剰電力も、単なる家庭内消費にとどまらず、社会全体を支える重要な資源となっていくでしょう。
まとめ
太陽光発電で生まれる余剰電力は、決して「捨てられる」ものではありません。
電気はエネルギーであり、必ず何らかの形で活用される必要があります。
卒FIT後も、同じ電力会社との再契約や高価格での売電先への乗り換え、自家消費、新しい仕組みである地域新電力やP2P取引への参加など、さまざまな選択肢が用意されています。
どの選択肢を取るかは、家庭ごとのライフスタイルや価値観によって異なります。
手間をかけず安定した売電収入を得たい方もいれば、少しの投資をして自家消費を最大化し、長期的な光熱費削減を目指す方もいるでしょう。
あるいは、地域社会に貢献したい、最新の仕組みに挑戦してみたいという方もいるかもしれません。
いずれにしても、卒FIT後に適切な判断をすることが、太陽光発電をより豊かに、そして賢く活用するための第一歩です。
あなた自身の生活に合った方法を選び、大切なエネルギー資源を最大限に活かしていきましょう。