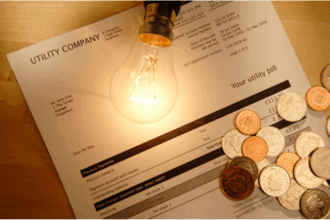太陽光発電は、電気代の負担を抑えつつ災害時の備えにもなることから、多くの家庭や事業者の注目を集めています。特に近年は蓄電池との併設によって日々の省エネ効果が高まり、停電時でも生活を止めずに済む頼もしさを実感する声が増えています。
しかし、導入にあたっては初期費用がどうしても大きくなりがちで、費用対効果が見合うのか迷う方も多いでしょう。そこで鍵を握るのが、自治体や県が用意している各種の補助金制度です。鳥取県でもさまざまな支援策が設けられており、制度の内容や条件をよく理解して上手に組み合わせることで、導入負担を大幅に削減することが可能になります。
このガイドでは、鳥取県が実施している太陽光発電・蓄電池の補助制度を中心に、導入によるメリット、申請にあたっての注意点などを詳しく紹介していきます。補助金の枠が限られていることも多いため、気になる方は早めに情報収集を始めてみてください。
鳥取県で太陽光補助金を受けられる4つのメリット
ここからは、実際に太陽光発電や蓄電池を導入することで得られる4つの大きなメリットを取り上げます。導入費用の高さに不安を感じる方も少なくありませんが、補助金を活用すればそのハードルを下げられるだけでなく、さまざまなメリットを同時に享受できます。
具体的にはどんな効果があるのか、順番に見ていきましょう。
初期費用の大幅な負担軽減
太陽光発電の導入には、本体機器や施工費など合わせてそれなりの費用が必要になりますが、鳥取県や県内の市町村が用意している補助金を活用することで、初期投資額を抑えることができます。
たとえば、鳥取県の「太陽光発電システム補助金」は3.6万円/kW(上限18万円)を支給する仕組みで、一定の条件を満たせばその分を導入費から差し引けます。市町村によっても独自の補助金があり、倉吉市は7万円/kWh(上限40万円)を蓄電池向けに支援するなど、導入時の手立てが豊富です。
売電収入と電気代削減の両立
太陽光発電を導入すると、日中に自宅や事業所で発電した電気を自家消費できるようになるため、電力会社から購入する電力量が減り、毎月の電気代を下げる効果が期待できます。
さらに、使いきれずに余った電力を売電すれば収入につながる点も大きな魅力です。こうした経済効果は長期的に見れば無視できない金額になることも多く、補助金と合わせて導入コストを回収するスピードを高められるでしょう。
とりわけ鳥取県のように日照時間が比較的安定している地域では、発電量が見込みやすい点もメリットの一つです。
蓄電池併設時の追加メリット
近年は太陽光発電と蓄電池をセットで導入するケースが増えています。
昼間に発電した電気を蓄電池へ充電しておけば、夜間や天気が悪い日の電力需要にも対応できるので、さらに高い自家消費率を実現し、電気代を抑えやすくなるというメリットがあります。
鳥取県の「蓄電池補助金」は5万円/kWh(上限20万円)を支給しており、V2H(Vehicle to Home)の設備と同時に申請する場合も補助対象になることがあります。
倉吉市では蓄電池に対して7万円/kWh(上限40万円)、日南町でも7万円/kWh(上限28万円)といった制度があり、それぞれの条件に合致するかどうかで支給額が変わります。導入費用が高額になりがちな蓄電池でも、こうした支援制度を使えば導入ハードルを低くできます。
災害時の非常用電源確保
鳥取県は地震や台風などの自然災害と無縁ではなく、突発的な停電が発生するリスクも否定できません。太陽光発電や蓄電池があれば、災害時でも最低限の電力を確保することができ、冷蔵庫やスマートフォンの充電などを継続できる点は心強いです。
V2Hを導入していれば電気自動車を電源として活用できるため、さらに強固なバックアップ体制が整います。補助金を活用して災害対策を強化できるというのは大きなメリットと言えるでしょう。
鳥取県の太陽光発電で利用できる3つの支援制度
メリットを踏まえたうえで、次は鳥取県内で利用できる代表的な3種類の支援制度に目を向けてみましょう。
県独自の補助金とあわせて、V2Hに対応した補助制度、市町村が独自に展開している補助金など、多面的なサポートが用意されています。
ここでは、それぞれの概要や申請条件をざっくりとつかんでおくことで、自分にあった補助制度を見極める手がかりを得ることができます。
県独自の住宅用太陽光補助金
鳥取県の「太陽光発電システム補助金」は3.6万円/kW(上限18万円)と、住宅向けとしては比較的手厚い部類に入ります。
対象となるシステムは1kW未満の太陽光発電設備が条件となり、導入前に未使用の製品であること、税金等の滞納がないことなどが求められます。
同時に「蓄電池補助金」5万円/kWh(上限20万円)も活用できる場合があり、その場合は設置価格の1/3までを支援する形となるのも注目ポイントです。
どちらも工事着工前の申請が原則であるため、導入を検討中の段階で必要書類や手続きについてチェックし、期限や受付枠に注意しながら動く必要があります。
V2H関連補助金の活用
近年注目を集めているのがV2H(Vehicle to Home)と呼ばれる技術で、電気自動車のバッテリーを蓄電池のように使い、家庭内に電力を供給できる仕組みを指します。
鳥取県では、蓄電池と同時に申請することを条件としたV2H補助金を設定しており、5万円/kWh(上限20万円)の支援を受けられるケースがあります。
電気自動車をお持ちの方や購入予定の方にとっては、家とクルマの両方の電源を一体的に管理する大きなメリットがあり、災害対策や電気代削減の幅がさらに広がります。
ただし、V2Hの機器自体はまだ高額なものが多いことから、補助金の活用方法や導入メリットをしっかり検討することが重要です。
市町村独自の補助金制度
鳥取県内の各市町村でも、県や国の補助金に上乗せする形で独自の補助金を用意しています。たとえば、境港市は4.6万円/kW(上限23万円)の補助制度を設けており、最大出力10kW未満の太陽光発電が対象になるなど、条件は自治体によってさまざまです。
倉吉市では7万円/kWh(上限40万円)の蓄電池補助金、湯梨浜町も3.6万円/kW(上限14.4万円)の太陽光発電補助金を提供しています。
南部町に至っては10万円/kW(上限60万円)と高額な補助を行う代わりに、発電量の30%以上を自家消費すること、FITやFIP制度の認定を取得しないことなど厳格な条件がつけられています。
日南町は7万円/kWh(上限28万円)で蓄電容量が10kW未満のものに対応するなど、それぞれ独自の条件があり、国や県の補助金との併用ができる場合もあります。ただし、南部町のように国補助金との併用不可という制限があるケースもあるので、各自治体の公式サイトや窓口で制度要綱をよく読んでから申し込むのが確実です。
鳥取県の太陽光補助金申請で失敗しない3つのポイント
ここまで説明してきたように、鳥取県内には多彩な補助金制度が存在し、自分に合った組み合わせを見つければ初期コストを大きく削減することができます。
しかし、申請にあたっては期限や手続き方法など、気をつけるべき点がいくつもあります。ここでは失敗しないために押さえておきたい3つの重要ポイントを紹介します。
申請時期と予算枠の確認手順
まず第一に、各補助金は年度ごとの予算枠が設けられており、申請期間も限られています。予算が上限に達した段階で受付を終了してしまうこともあるため、導入を考え始めたら早めに県や市町村の公式サイト、あるいは窓口で最新の情報を集めておく必要があります。
思い立ったときにすぐ工事を始めてしまうと、着工前申請が必須なのに手続きを忘れていたというケースも起こり得ます。業者と相談しながら、いつ着工するか、どのタイミングで申請書類を出すかをスケジュールに組み込んでおくことが大切です。
必要書類の準備と提出方法
補助金の申請では、工事見積書や設置予定の機器情報、住民税の滞納がない証明など、複数の書類が求められます。
また、各自治体や県の制度によって提出先や書類の書き方が微妙に違う場合があるため、要項を丁寧に読み込み、書類の不備がない状態で提出することが不可欠です。
もし書類不備での再提出が続くと、その間に予算が終了してしまうリスクもあるので、業者だけに任せず、自分自身でも必要事項を把握しながら準備を進めたほうが安心です。
実績報告書の作成と期限管理
補助金は申請して終わりではなく、工事が完了したあとの実績報告まで確実にやり遂げることで、最終的に交付が確定する流れになっています。
設置前後の写真や施工内容がわかる資料などを用意し、決められた期限内に報告書を提出することが原則です。報告を怠ったり期限を過ぎたりすると、補助金が支給されないばかりか、補助金がすでに交付されていた場合は返還義務が生じるおそれもあります。
着工前・着工中・完工後の3つのフェーズでどの書類が必要かをあらかじめ確認し、業者との連携を取りながら確実に進めましょう。
まとめ
これから鳥取県内で太陽光発電や蓄電池を導入しようと考えている方は、まずは県や市町村の公式サイトをチェックし、申請条件とスケジュールをよく確かめましょう。
業者のなかには補助金申請のサポートを行っているところもあるため、相談しながら効率よく準備を進めるのがおすすめです。
見積もり段階で工事費や機器費用とあわせて補助金適用後の費用シミュレーションも出してもらうと、費用対効果がイメージしやすくなります。最適な制度を見極め、時間に余裕をもって申請手続きを終わらせ、災害にも強いクリーンエネルギーライフをスタートしてみてはいかがでしょうか。