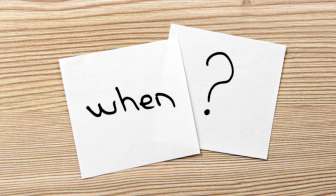停電が起きたとき「太陽光発電があるから安心」と思っていませんか?
実は、太陽光発電システムだけでは、停電時には使えないこともあるんです。
しかし、事前に正しい準備と知識を身につけておけば、停電時でも太陽光の電力を有効活用でき、家族の暮らしを守ることができます。
さらに、蓄電池を導入すれば、夜間や悪天候時にも電力を確保できるため、災害時の安心感は格段にアップ。
この記事では、「太陽光発電が停電時に使えない理由」から「使えるようにする具体的な方法」、さらに「実際に役立った事例」まで詳しく解説します。
万が一の時にも「電気が使える家」でいるために、今からできる準備を一緒に考えていきましょう!
太陽光発電は停電時に使えないって本当?
災害やトラブルによって停電が発生したとき、「太陽光発電があるから安心」と思っている方も多いでしょう。
しかし、実際には、太陽光発電システムがすぐには使えないケースが存在します。
理由は、太陽光発電システムが通常「電力会社の送電網(系統)」に連携して運転しているからです。
停電が起こると、この連系運転は安全のため自動的に停止し、たとえ太陽が照っていても発電した電気を家庭で利用することはできません。
ただし、完全に無力なわけではありません。
「自立運転」という非常時専用のモードに手動で切り替えることで、発電した電力を一部使えるようにすることが可能です。
この操作を知っているかどうかが、停電時に太陽光発電を活かせるかどうかを左右します。
停電時に太陽光発電を使うための準備と注意点
太陽光発電システムを停電時に使うには、あらかじめいくつかの準備と注意点を理解しておく必要があります。
まず、「自立運転モード」への切り替えが必須です。
各メーカーや機種ごとに方法が異なるため、日頃から取扱説明書を確認しておきましょう。
特に、非常用コンセントの設置場所と仕様を知っておくことは重要です。
さらに、停電時には使用できる電力が制限される点にも注意が必要です。
一般的に最大出力は1500W前後で、これは家庭全体をカバーするには不十分な容量です。
また、雨天や曇天、夜間には発電量が大幅に低下またはゼロになるため、過信はしないようにしましょう。
使える電力量と使えない家電の見分け方
自立運転で使える最大電力(例えば1500W)を超えない範囲で電気機器を使用する必要があります。
たとえば、以下のような家電製品は比較的使いやすいです。
家電名 使用電力 携帯電話の充電 数W〜10W 扇風機 20〜40W LED照明 5〜20W 小型テレビ 50〜100W
一方、以下のような消費電力が大きい家電は注意が必要です。
家電名 使用電力 電子レンジ 1000W以上 エアコン 数百W〜1kW以上 電気ケトル 1200W以上
これらを同時に使うと、すぐに容量オーバーしてしまいます。
非常時には、「命を守るために必要最低限の電化製品だけを使う」という意識が大切です。
非常用コンセントの位置と使用条件を確認
停電時に太陽光発電の電力を使うには、専用の非常用コンセントから電力を取り出す必要があります。
通常使っている家中のコンセントでは利用できないため、注意が必要です。
非常用コンセントは、設置工事の際にパワーコンディショナ(パワコン)付近や分電盤の近くに設置されているケースが多く、見た目は通常のコンセントと似ていますが、ラベルや色分けで区別されていることもあります。
設置場所がわからない場合は、事前に施工業者に確認しておきましょう。
また、非常用コンセントには以下のような使用条件があります。
- 最大出力は1500W程度に制限されている(超えるとブレーカーが落ちる)
- 天候に左右されるため、曇りや雨の日は使える電力量が減る
- 夜間は使用できない(発電しないため)
- パソコンや医療機器など精密機器は推奨されない(電圧変動リスクあり)
非常時に慌てないためにも、日頃から非常用コンセントの場所を把握し、どの家電をどれくらい使えるかを想定しておくことが大切です。
【蓄電池】停電時でも太陽光発電を使えるようにする方法
太陽光発電だけでは、夜間や天候が悪い時に電気を使えないという弱点があります。
その課題を解決するのが蓄電池の存在です。
蓄電池があれば、昼間に発電した電力を貯めておき、夜間や曇りの日にも必要な電気を使うことが可能になります。
特に長期間の停電が想定される地震や台風の際には、「太陽光+蓄電池」のセットが、圧倒的な安心感をもたらします。
ここでは、蓄電池を選ぶ際に押さえておきたい基本情報を整理していきましょう。
蓄電池の種類と選び方
蓄電池には、大きく分けて次の2つのタイプがあります。
タイプ 特徴 向いている人 特定負荷型 家の一部の回路だけに電気を供給する。コストが抑えられる。 コスパ重視で最低限の電気を確保したい人 全負荷型 家中すべての回路で電気が使える。停電を意識しない生活が可能。 快適さを重視し、予算に余裕がある人
特定負荷型は比較的リーズナブルですが、使えるコンセントや家電が限られます。
一方、全負荷型はどの部屋でも通常通り電気が使える反面、価格が高くなる傾向があります。
自分たちのライフスタイルや予算に合わせて、適切なタイプを選ぶことが重要です。
蓄電容量はどれくらい必要?
蓄電池選びで重要なのが、「どれくらい電気を貯めておきたいか」です。
目安として、一般的な家庭で1日に必要な電力は約10〜12kWh程度とされています。
これに対し、よく販売されている家庭用蓄電池の容量は、以下のとおりです。
容量目安 使える範囲 備考 5〜7kWh 照明・スマホ充電・テレビなど最低限の生活 軽量・低コスト 10〜14kWh 照明・冷蔵庫・テレビ+α バランス型、人気 15kWh以上 ほぼ通常通りの生活が可能 高価格帯
特に、冷蔵庫や携帯電話の充電は、災害時に命に直結するため、最低でも10kWh前後を確保できる蓄電池が安心です。
蓄電池選びで失敗しないためのポイント
蓄電池選びで失敗しないためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 保証期間と耐用年数を確認する(10年保証が目安)
- 設置スペースを事前に確認する(室内用か屋外用か)
- V2H対応(電気自動車連携)が必要か考える
- 補助金・助成金制度を活用する
また、停電時だけでなく、電気代節約(ピークシフト)目的でも使いたい場合は、充放電サイクルや制御機能もチェックしておきたいところです。
【実例】停電時に太陽光発電が役立った2つのシーン
ここでは、実際に災害時に太陽光発電システムが役立ったケースをご紹介します。
どちらも、「もしもの時の備え」として、太陽光発電と蓄電池がどれだけ心強いかを実感させてくれる実例です。
①地震時
2011年の東日本大震災では、多くの地域で大規模な停電が発生しました。
この時、自宅に太陽光発電システムを導入していた家庭のなかには、昼間だけでも携帯電話の充電や最低限の照明確保に成功したという声が多くありました。
特に、太陽光発電+蓄電池を設置していた家庭では、日中に発電した電気を冷蔵庫やスマホ充電に活用したり、夜間も蓄電池に貯めた電力で照明や小型家電を使用したりと、ライフラインの寸断による不便を大幅に軽減できたとの報告もあります。
非常用コンセントや自立運転への切り替えを日頃から訓練していたかどうか、普段からの準備が、停電時に差を生みました。
②台風時
近年、強力な台風による大規模停電が各地で発生しています。
例えば、2019年の台風15号(関東地方)では、1週間以上電気が復旧しなかった地域もありました。
このとき、太陽光発電を設置していた家庭では、日中の発電電力で扇風機やスマホを使用したり、夜間は最低限の照明だけ蓄電池でまかなって生活を維持したり、外部電源が不要だったため避難所に行かず自宅待機が可能になったりと、たくさんのメリットを享受できました。
特に小さな子どもや高齢者のいる家庭では、エアコンや冷蔵庫が使えなかった場合の健康リスクが非常に高まるため、自宅で最低限の電力を確保できたことは、とても大きな安心材料になりました。
【まとめ】停電時に使えないを避けるために蓄電池を導入しよう!
停電時に「太陽光発電が使えない」という事態は、知識と準備次第で十分に防ぐことができます。
まず、太陽光発電システムが停電時に自動的には使えない理由を理解し、自立運転モードへの切り替えをスムーズにできるようにしておくことが重要です。
また、停電時に使用できる電力量や、非常用コンセントの設置場所・条件についても、事前に家族全員で確認しておきましょう。
さらに、蓄電池を併用することで、太陽光発電の弱点(夜間や天候不良時に発電できない問題)をカバーできます。
特定負荷型・全負荷型の違いや、自宅に必要な蓄電容量を把握して、ライフスタイルに合った製品を選ぶことが、停電への最強の備えとなります。
災害大国・日本に住んでいる私たちにとって、「もしものとき、家に電気がある」という安心感は、何にも代えがたいものです。
停電に強い家づくりを進めるためにも、太陽光発電と蓄電池の導入をぜひ検討してみてください。